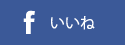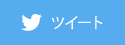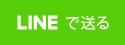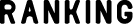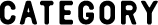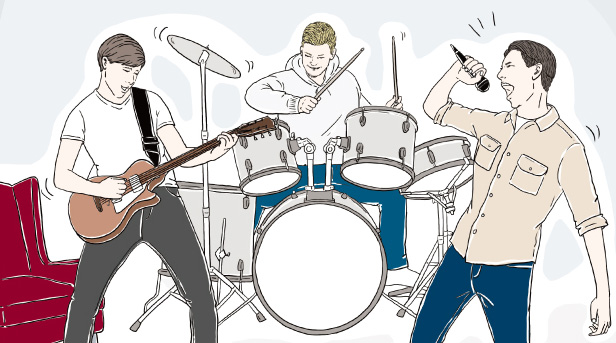自宅で楽器の練習をしたい人や、音楽教室を開きたい人は、「防音室」が必要になりますよね。とはいえ、「そもそも防音室って作れるの?」「音楽教室を開くには専用の部屋を借りなければならないの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
最近ではYouTubeなどでのライブ配信を仕事にしている人も増えてきて、防音室の需要は高まってきました。
そこで今回は、防音室についての基礎知識から、相場や工事について解説していきます。音漏れを防ぎ、音響のいい部屋で楽器や会話を楽しんでくださいね。
1.そもそも「防音室」ってなに?
「防音室」と聞いても、いまいちピンとこない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
防音室とは、室内の音漏れ・外からの騒音を防いだり、音響をよくしたりする部屋のこと。ただ音を遮るだけでなく、音色や声を美しく聞こえるようにもしてくれるんです。
楽器を演奏する人にとっては奏でる音を鮮明に聞くための部屋でもあり、配信者にとっては視聴者へクリアな音を届けるための部屋でもあります。防音室の設置は騒音対策になるだけでなく、音を発する側・聴く側へ、ここちよい音を届けることにも繋がるのです。
2.防音室はどんな部屋に有効?使い方4つ
「防音室によって音漏れ・騒音・音響の改善がされる」とお伝えしましたが、どんな部屋に有効なのか、おすすめの使い方も知りたいもの。
防音室というと、スタジオや音楽室のような本格的な部屋を想像しちゃいますよね。しかし実際は普通の部屋と変わらず、インテリアだっておしゃれに楽しめるんです。
そんな防音室は、下のような部屋に効果を発揮します。
①リビング
②楽器部屋
③ホームシアター
④オーディオルーム
例えばテレビの音や話し声が気になる「リビング」、ピアノやギターを演奏できる「楽器部屋」。その他にも、映画を鑑賞する「ホームシアター」、音楽を好きな音量で聞ける「オーディオルーム」など。気になる音漏れや音響へのこだわりも、防音室がすべてクリアしてくれちゃうんです!
「本格的に音楽を楽しみたい」「家に自分だけの映画館を作りたい」など、そんな夢や理想を叶えたい方は、ぜひ防音室を取り入れてみてくださいね。
3.防音室を作るときに考えたい3つのこと

楽器部屋だけでなく、リビングやホームシアターなどにも使える防音室。ですが、音が防げれば何でもいいというわけではありません。
ここからは自宅に作るときにチェックすべき3つのポイントをご紹介するので、リフォームする際の参考にしてくださいね。
3-1. ポイント1 遮音
「遮音」とは空気を伝わってくる音を遮断することで、防音のなかの1つ。「空気を伝わる音」を空気音といい、人の話声・楽器の音色・歌声・テレビの音などを指します。
これらの音が外へ漏れるのを防ぐので、騒音トラブルも防止。周りを気にすることなく、楽器の練習にも打ち込めちゃうんです。
しかし遮音性が高すぎると音の反響が大きくなってしまうので、実際の音と耳で聞く音が違ったり、聞こえにくくなったりすることも。ですので、遮音だけにこだわるのではなく、これからご紹介する吸音・音響を調整することで、よりよい防音室を作ることができます。
3-2. ポイント2 吸音
「吸音」とは音を吸収して防音すること。室内の音を吸収して外に漏れることを防いだり、音の反響を抑えたりしてくれます。
遮音と吸音を組み合わせることで、遮音だけでは反響して音が聞こえにくくなる点を改善し、より音が鮮明に聞こえるようになるのがメリットです。
反対に、吸音性が高くなりすぎると詰まったような音になり、楽器や歌の練習がしにくくなることも……。なので、防音室を作るときは遮音性と吸音性をうまく調整し、ちょうどいい反響と音漏れの軽減を実現させることがポイントです。
3-3. ポイント3 音響
遮音と吸音が組み合わせることで、「音響」を調整できます。音響は楽器の演奏やオーディオルームにはかかせないもので、同じ音でもまったく違う音に聞こえるんです。
よりクリアな音が聞きたい人や、楽器・歌の練習を向上させたい人は、遮音性・吸音性を調整して、音響を改善してみましょう。
4.遮音性能を計算して防音室を作ろう
遮音・吸音によって防音室は作られますが、じつは目指す音の大きさによって性能を選ばなくてはなりません。これを「遮音性能」といい、以下の計算式によって算出されます。
「室内の音の大きさ-室外で聞こえる音の大きさ=遮音性能」
| 音の大きさ | 音の種類 |
| 120dB | ジェット飛行機の近く・オペラ |
| 110dB | アルトサックス・ドラム |
| 100dB | 電車のガード下・ピアノ・トランペット |
| 90dB | 騒々しい工場・大声による独唱・バイオリン・フルート |
| 80dB | 地下鉄の車内・クラシックギター |
| 70dB | 騒々しい事務所・電話の着信音 |
| 60dB | ふつうの話し声 |
| 50dB | 静かな事務所 |
| 40dB | 深夜の市内・図書館 |
| 30dB | ささやき声 |
| 20dB | 木の葉の音 |
計算するときの参考になるのが、上の表。人が「静か」と感じる40~50dB以下の音の大きさを目指すのがポイントです。
例えば、ドラムの練習部屋を作る場合は「110dB(ドラム)-50dB=60dB(遮音性能)」が必要。歌の練習部屋を作るのであれば、「90dB(ドラム)-50dB=40dB(遮音性能)」の防音室を作らなくてはなりません。
ご紹介した計算式と音の表を、防音室を作るときの参考にしてくださいね。
5.防音室を作るときに取り付けるもの
音を遮断して、音響まで改善される防音室ですが、「工事は大掛かりになるの?」「何を使うの?」なんて疑問も。そこでここからは、部屋を防音室にリフォームするときに取り付けるものをご紹介していきます。代表的なものは、以下の3つです。
5-1.防音パネル
「防音パネル」とは、遮音・吸音してくれるパネルのこと。本格的にリフォームする際は分厚い防音パネルを設置し、外への音漏れをきちんと防いでくれます。反対に自分で設置できる厚さ5センチほどのものもあり、DIYも可能です。おしゃれなデザインのものからシンプルなものまでさまざまで、インテリアとしても楽しめるのが嬉しいポイント。
5-2.調音パネル

画像引用:YAMAHA
「調音パネル」は、音響を調整してくれるもの。室内の音の響きを調整し、反響しすぎ・吸収しすぎを改善します。
壁に貼るタイプのものもあれば、足付きの立てられるタイプも。かんたんに設置できるので、音にこだわりたい人におすすめです。
YAMAHAからも調音パネルが販売されており、価格は36,000円(税抜)から。数枚設置するだけで音響が変わる、演奏やリスニングに最適な商品です。
5-3.防音ドア
通常のドアだと、床から1センチほど隙間が空いていますよね。空気が通りやすくなったり、開け閉めしやすくなったりしますが、じつは音漏れの原因はその隙間。
そんな隙間を密閉してくれるのが「防音ドア」です。ドアとドア枠、ドアと床との隙間を密閉するハンドル「グレモン錠」と「高気密パッキン」がついたドアのことを言います。

画像引用:小林スチール工業
防音ドアにもさまざまな種類があり、スタジオで使用されるような防音ドアだと、小林スチール工業の「ドラム室用防音ドア」

画像引用:大建工業
リビングになじませたいなら、大建工業の「アドバンス(A)防音タイプ」
上記の商品がお勧めです!
6.防音室にお家をリフォーム!相場と工事日数は?

本格的な防音室を作るのであれば、リフォームしたいところ。となると、相場や工事日数が気になりますよね。
じつはリフォームにかかる費用は、遮音性能を高くすると、費用も高くなります。そのぶん使用する材料の質がよくなったり、量が増えたりするからです。
相場としては、部分的に防音する場合は、1㎡あたり5万円から。防音リフォームする場合は、1㎡あたり10万円から。部分的な防音であれば1日、6畳のリフォームでおよそ3~4日の工事日数が目安です。
リフォームとなると費用も高くなってしまいますが、遮音性能は保証されているので安心ですね。
7.リフォームだけじゃない!ユニット式防音室を置ける

画像引用:YAMAHA
リフォームについてご紹介しましたが、防音室はそれだけじゃありません!「ユニット式」の防音室もあることをご存知ですか?
ヤマハのユニット式防音室に、「アビテックス ユニットシリーズ」があります。
0.8~4.3畳まであり、0.8畳なら歌の練習、2.0畳で音楽制作ルーム、3.0畳でクランドピアノに使用可能。使い方に合わせて広さを選べるうえ、自宅をリフォームしたくない方にとっても嬉しいですよね。
8.まとめ
防音室は楽器の練習以外にも、歌の練習・ホームシアター・リビングなど、さまざまな使い方ができます。これらの部屋の音漏れを防ぐだけでなく音響も改善されるので、音にこだわりたい人にとっても嬉しいですよね。
とはいえ、リフォームだと費用が高くなってしまうので、まずは防音パネルや調音パネルを使ったDIYをしてみるのもおすすめ。「もっと遮音したい・音響をよくしたい」と感じたら、自宅のリフォームや防音マンションへの引越しを検討してみてくださいね。